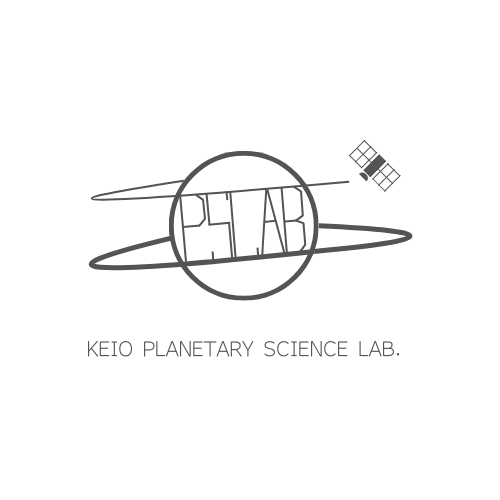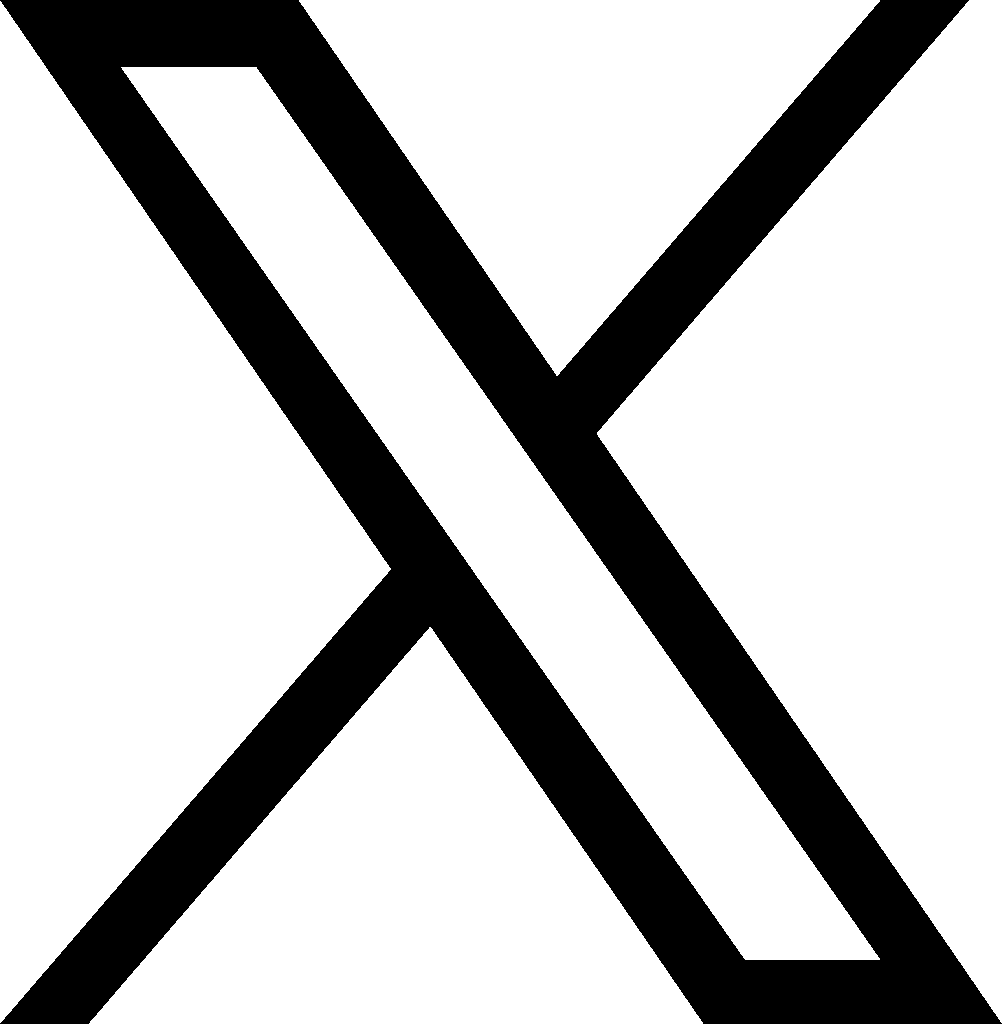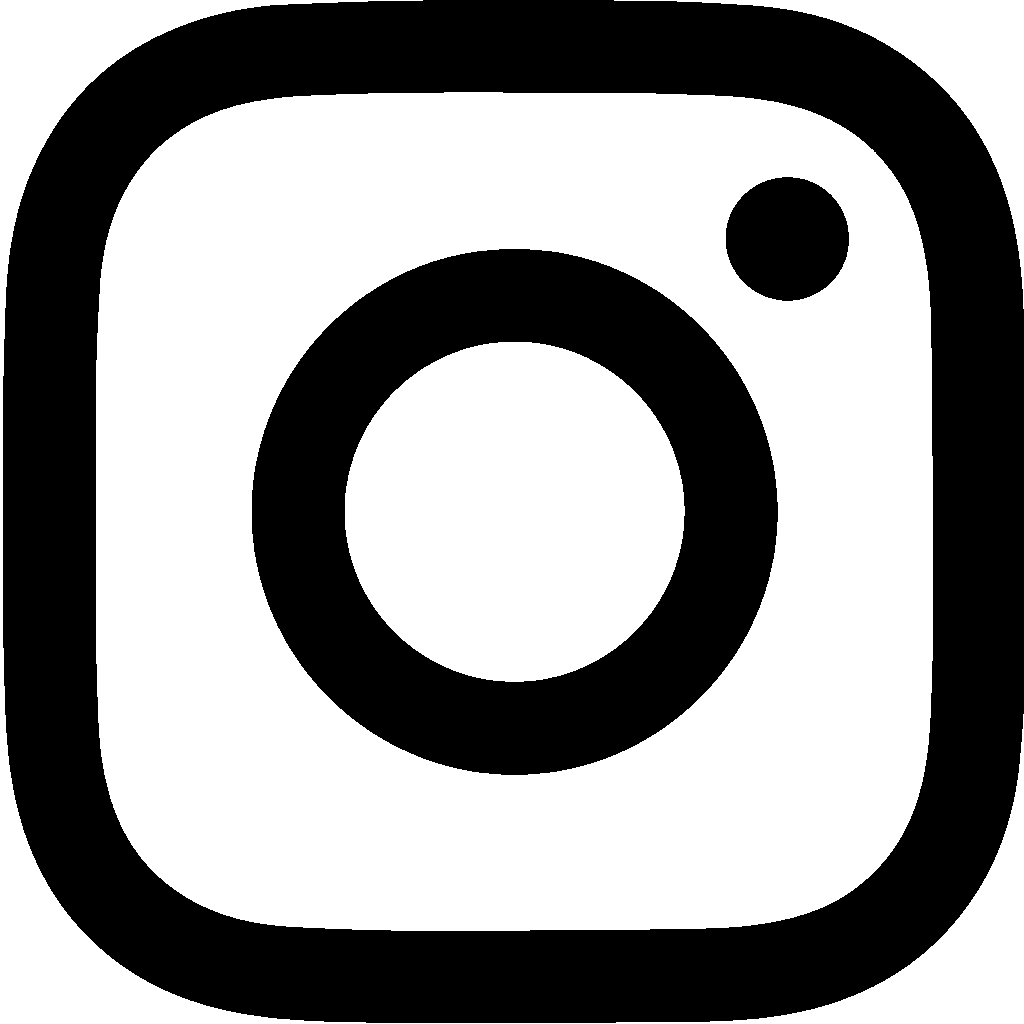以下は慶應義塾大学環境情報学部、総合政策学部、大学院政策・メディア研究科に所属する学生向けの情報となっております。
1.研究会概要
惑星圏科学研究会では、惑星科学の知識を最大限活用することで、惑星進化を明らかにするための研究課題や、惑星の「いま」を理解するための課題に取り組みます。また、宇宙・惑星科学を基盤に新たな学問分野を開拓します。具体的な研究テーマは個別に相談しながら決めていきます。研究は主に数値シミュレーションや探査機等のデータ解析を行うことで進めていきます。
本研究会では、「惑星圏」で生じるさまざまな現象について、物理的・化学的視点からその原因を明らかにし、問題解決能力を養うことを目標とします。特に、惑星プラズマや惑星大気環境を通じて惑星の進化を理解するための基礎研究や、惑星探査機のデータ解析から惑星で生じている「素過程」を解明する研究課題に取り組みます。さらに、文理融合型の研究にも関心を持ち、文系的アプローチによる新たな研究分野の開拓にも取り組んでいく予定です。
各回の研究会では、教材を用いた輪講や、数値シミュレーションまたはデータ解析の実習、そして個々の研究に取り組みます。物理学や数学の素養があることが望ましいですが、文系的アプローチに関心がある場合はその限りではありません。その場合は、どのような研究に取り組みたいかについてある程度のビジョンを持っていることが必須です。また、英語論文を読むための語学力やプログラミングの経験があれば、なお望ましいです。
2.主な研究内容
以下のテーマを軸に、教員と相談しながら具体的な研究テーマを決定し、個人もしくはグループで研究を行います。主体的に取り組める研究であれば、必ずしも以下のテーマに限る必要はありません。惑星圏科学の研究は、日本国内のみならず、世界中の大学や研究機関と共同で実施されているものが多数あります。皆さんには、研究手法の習得や議論を深めるために、国内外の大学や研究機関に赴いて学んでもらうこともあります。また、本研究会はアウトリーチ活動にも力を入れています。研究内容に関連する現象を一般向けに紹介する出前実験や講演会なども、今後企画していく予定です。
主な研究対象
・火星、金星、系外惑星、木星 (衛星含む)、土星 (衛星含む)、(過去)地球、(水星)、など
研究手法
・数値シミュレーション
磁気流体力学 (MHD) シミュレーション、テスト粒子シミュレーション、電子輸送シミュレーション、光化学シミュレーション、(ハイブリッドシミュレーション、Particle in Cell (PIC) シミュレーション)
・探査機データ解析
火星探査機MAVEN、火星探査機HOPE/EMM、土星探査機Cassini、(火星探査機Mars Express、TGO、木星探査機Juno、水星探査機BepiColombo)
※ 括弧付きは研究開始までに準備が必要なもの。
主な研究テーマ
・大気流出研究 [大気進化研究]
・火星電離圏研究 (オーロラ研究含む) [大気進化研究、物理素過程研究]
・金星電離圏研究 [大気進化研究、物理素過程研究]
・木星・土星衛星水調査 + 周辺環境研究 [惑星進化研究、生命探査]
など。主体的にできるものであれば上記以外も可。
研究会・来期の研究プロジェクトテーマ予定
・大気流出研究 [大気進化研究]
・火星電離圏研究 (オーロラ研究含む) [大気進化研究、物理素過程研究]
・金星電離圏研究 [大気進化研究、物理素過程研究]
・木星・土星衛星水調査 + 周辺環境研究 [惑星進化研究、生命探査]
・地球オーロラ [物理素過程研究]
・その他
3.新規履修希望者へ (2026年春)
【履修希望者登録フォーム】
履修希望者は、2月10日(火) までにK-LMSより申請してください。なお、2月12日(木)から2月27日(金)のいずれかの日程で、リモート面接を実施する場合があります。
課題選抜用URL:https://lms.keio.jp/courses/sis_course_id:MA2026-A04-senbatsu-3-49515
シラバスURL:https://gslbs.keio.jp/pub-syllabus/detail?ttblyr=2026&entno=32892&lang=jp
【研究会説明会】
以下の要領で研究会の説明会を実施します。参加を希望される方は、下記フォームより登録してください。なお、説明会への参加は履修の必須条件ではありません。
日時:2月4日(水)13:00-14:00
参加登録フォーム:https://forms.gle/FQkXqnZCHjeSNrex8